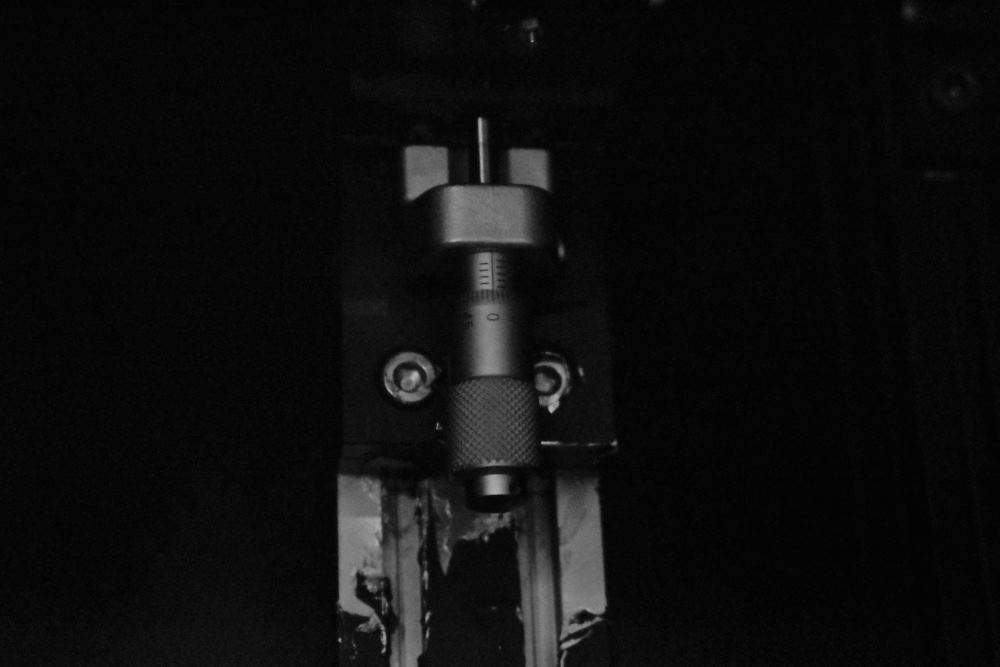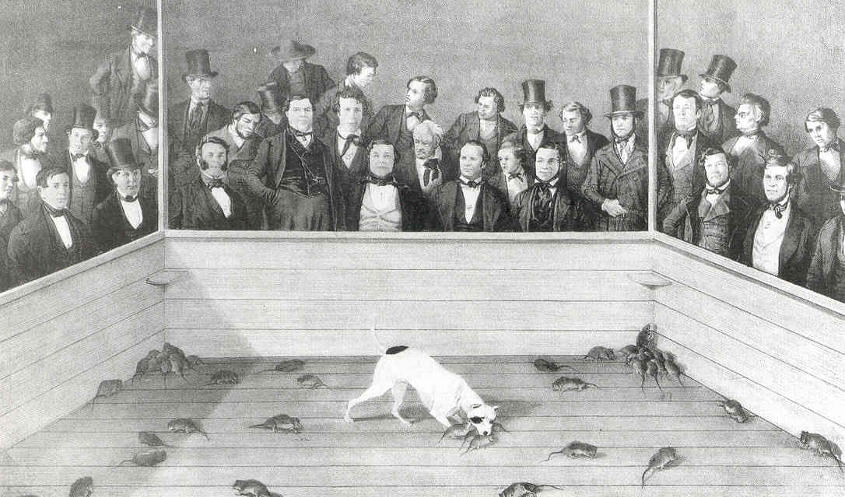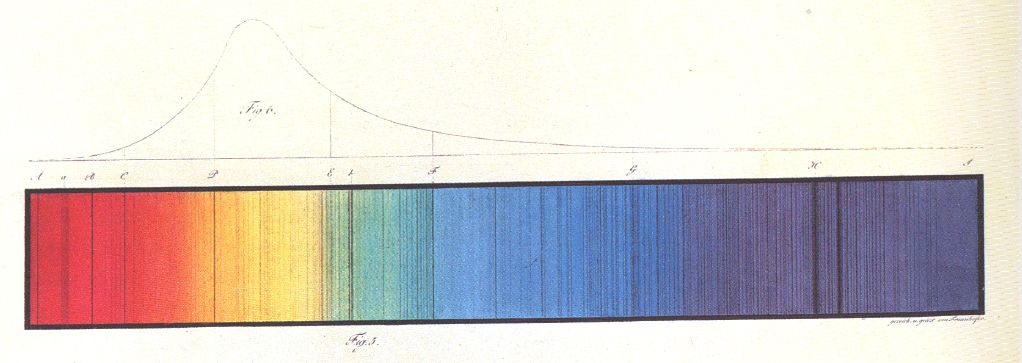政府が人々の経済的自由を制限し、国家権力が統制するようになっていくと、人々は自分の人生を自分で選んで幸福を追求することが出来なくなってしまう。
市場競争にさらされない政府のサービスは、必然的に画一的になり、品質も低下していく。日本でも、ほとんど全ての人にとって割安とは言えなくなり、だがそれにもかかわらず、税負担を強制されているサービスが無数にある。
政府は、利回りがマイナスの年金を押し付けたり、十分な保険をかけずに事故を起こす原子力発電所を押し付けたり、適合できなくても逃れることのできない教育を税金を使って強制的に押し付けたりする。自由な市場では選択されないような品質のものを、政府の強制力によって押し売りしているのである。そして、政府とは本質的にそういう性質のものなのである。
政府のサービスは額面だけは無償だったり格安だったりするけれども、結局は税金として負担するので実質的に割高である。人々はそれを使い続ける。自分が使わなくても、他人は使うのであるから、税負担は続く。だから、使わなければ損になってしまうのである。
いつしか政府の統制下で決められた製品やサービスしか選べなくなってしまい、政府が良いと言ったものしか選ぶことができなくなる。政府の範囲が拡大するとき、自由は失われる。そこにあるのは国家に人生を統制された社会である。
政府は人々から直接的に私有財産を引き離し、政府の裁量によって使途を決めてしまう仕組みをいくつももっている。たとえば税金や、社会保険料の徴収、政府の紙幣発行に伴うインフレ税、様々な形で人々の経済的自由を奪っていく。同時に、公営社会保障や公教育、公共事業といった、公金の支出によるモノやサービスに人々を依存させることで、経済的自由を奪っていく。
人々が代替の選択肢を選ぶことができなくなると、不合理を強制されてしまう。経済的自由が失われて国家によって統制された社会では、政府の失敗によって膨大な不合理が社会全体に放置される結果が導かれる。
人々が自分で選んで幸福を追求するための基礎となるのは、経済的自由である。経済的自由を失った人々は、職業選択の自由を失い、教育を選択する自由を失い、他者を助ける余裕を失う。もはや自由に選択して生きることができなくなれば、不満があっても逃れることができないから、奴隷と同じである。
経済的自由を喪失した人々は、与えられたものを受け入れなければならなくなってしまうから、必然的に権力に隷属させられるのである。
人々が政治に頼る限り、窮屈な状況に不満をどれだけ叫ぶとしても、解決する手段にはならない。それどころか、より一層窮屈な状況に自分たちを追い込むことになるだろう。
http://shibari.wpblog.jp/archives/13973
http://shibari.wpblog.jp/archives/14151