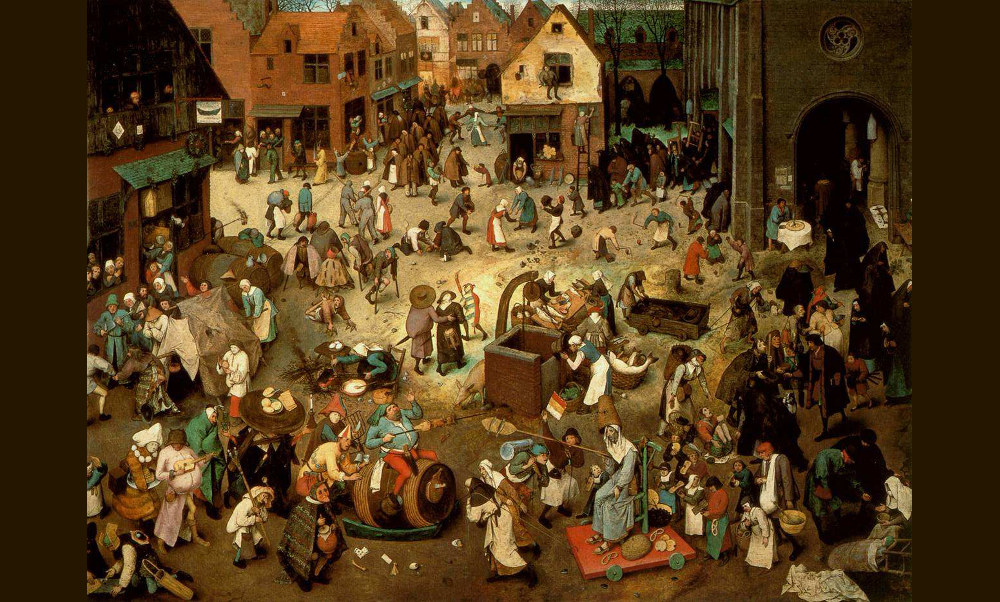いうまでもなく、公権力でもって自由を制限してはならない。けれども、自由な判断の結果については本人の責任である。ここでいう責任とは、もちろん政府によって処罰されるべきであるという話ではない。
私の表現が気に入らない誰かが私と会話することを拒否するとしても仕方ない。私との取引を拒否するとしても仕方ない。他者の身体や財産の自由を侵害する権利は私にはない。 「一定の」ではなく「明確に」責任を伴うと言えると思う。責任を説明するのに、法律は必要ない。
財産権が明確に尊重されている社会では、自由だからと言って乱暴なことをしたら生きていくことが難しい。多くの人に取引を拒否されれば、自給自足するしかなくなるからだ。
逆に、財産の自由が失われると、自由というのはまったく乱暴なものになる。嫌な表現を耳にしても、税を介してその人の生活を保障しなければならない、それでは表現を拒否できない。このような前提では、もちろん乱暴な表現がまかり通るとしても仕方ない。
徴税や公営社会保障を肯定し、財産の自由を否定する人は、表現の自由を否定せずにはいられなくなる。
あらゆる自由の基礎として、財産権は極めて大切である。ヘイトスピーチが嫌なら、政府による自由の侵害、とくに財産権の侵害は、徹底的に否定したい。