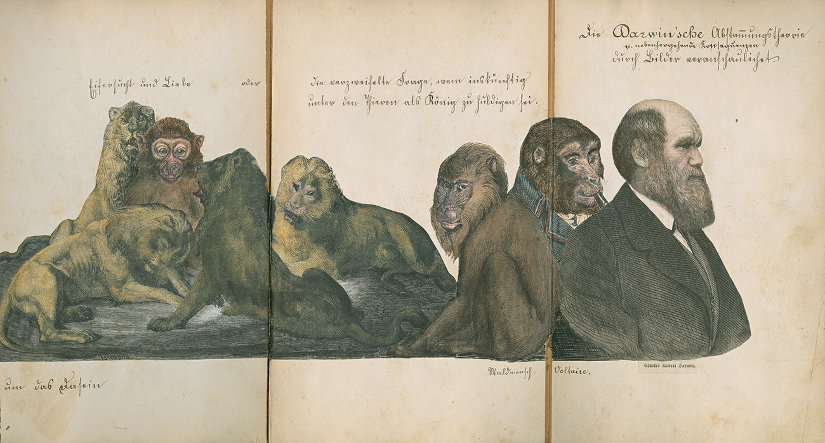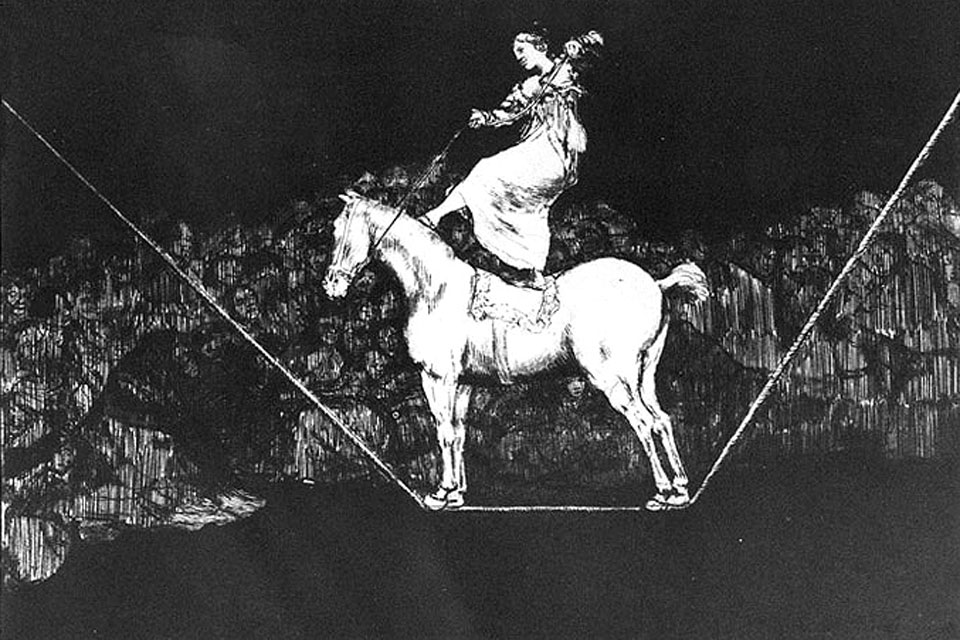トイレを使用するためだけにコンビニを利用する者が存在すると、その「フリーライド」が問題であるという人がいる。
もちろんこの発想は誤りで、コンビニの所有者には設置するかどうか判断する自由があるので何ら問題はない。トイレを維持するコストを自らの売る商品に転嫁してもそうしたほうが儲けが増えると思うから無償提供しているに過ぎない。
コンビニは私有財産権の範囲で自発的にトイレをタダで提供しているに過ぎず、トイレの提供は単に営業の一部である。逆に、損すると思うなら使用を禁止するのは所有者の自由であるし、利用者一人ひとりから料金を取るのも所有者の自由だ。結果的に損するか得するかは、所有者自身の責任なのであって、第三者が気に掛けることではない。
せっかくなので、問題のあるフリーライドについても考えてみよう。たとえば、政府がコンビニ経営者に無料トイレ提供を義務づけたとする。政府に設置を強制されたトイレを誰かがタダで使ったら、ここに生じる「フリーライド」は、先に述べたようなフリーライドとは全く意味が変わってくる。文字通り、コンビニの所有者がトイレの掃除を強制されている奴隷になってしまうのである。
問題のないものを問題だという人たちは、いったい何を主張したかったのだろう。実は、公衆トイレを税金で作れという話に展開しようとしたのである。
そこで、政府が税金を使って公衆トイレを作る場合を考えよう。ここでもコンビニの所有者にトイレの設置を義務付ける場合と同じ問題が生じる。公衆トイレを使いたい人のために、公衆トイレを使わない生活をしている人にまで負担させて公衆トイレを作ってしまうと、そこに不当な利権と搾取が生じるのである。
つまり、問題のあるものを作れと主張するために、問題のないものを問題だと言っていたことになる。このような政治的主張の危険性は、まずその第一段階で強制力によって労働させられる人を作り出していることにある。
さらに、話をもう一歩進めよう。政府の強制力によるフリーライドを一旦容認すると、民主主義によってそれを解決することが不可能になるということを指摘したい。
公衆トイレを作ることによって生じた搾取構造を解消するためには、政府が公衆トイレを廃止すればよい。これは論理的に明らかなのだが、現実の民主主義政府はさらに別の搾取構造を作ることで問題を拡大しながら先送りできてしまう。
政府は小さな搾取を作ることによって公衆トイレを使わない人の票を失うとしても、例えば、公営ゲートボール場を作ることで、公営ゲートボール場の利用者の票を獲得できるかもしれないからだ。公衆トイレを絶対に使いたくないと考える人よりも、ゲートボール場の潜在的な利用者の方が多ければ、後者が勝ってしまう。政府は、少しだけ大きな搾取を作り出せばよいのである。
民主主義は公衆トイレの廃止よりもゲートボール場を追加で作る方を選択してしまうから、もはや公衆トイレは廃止されない、さらに、公営ゲートボール場まで作られてしまう。次に公営ゲートボール場の不公平に気づく人もやがて出てくるとしても、政府は体育館を作ることができてしまう。その次に作られるのは博物館だろうか??? かくして、政府のすべての事業は利権となってどんどん巨大化していってしまう。
すべての利権が先行する利権を肯定しながらさらに票を獲得するために調整されたものでなのであるという事実に注意すると、膨らんだ政府の事業を民主主義によって少しずつ廃止縮小することはまったく不可能だということにも気づけるはずだ。
一部の政治利権を廃止してそのままにしようとすると、もともとある不公平が顕在化してしまう。その不公平をごまかしてさらに票を加えるために利権を組み立てているのだから、それを否定してしまう政党が選挙で勝てるはずがない。
だから、民主主義の選挙で議席を得るのは、すべての利権を廃止しようとする政党ではなく、すべての利権を曖昧に肯定しながら、さらに余計な利権を生み出す政党が勝てる政党である。一時的にいずれかの利権を廃止するとしても、政党はすぐにそれに代わる規模の利権を生み出して穴埋めせずにはいられなくなるのだ。