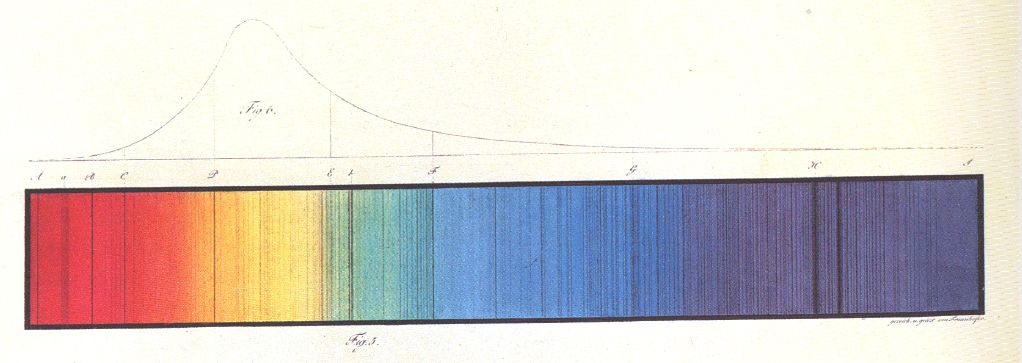「LGBTは生産性が低い」という杉田水脈議員の表現が話題になっている。まったく彼女の発言は批判されるべき性質のものだ。誰かが社会に「利益」をもたらさないからという理由で、不公平に扱われるべきではない。
そう、彼女は法の下の平等という考え方を無視したのである。
もっとも、法の下の平等という考え方が、常日頃から無視されがちであるということはちゃんと確認しておいた方が良いと思う。
たとえば、「子どもを作ることが、社会全体の利益だ」といって子育て「支援」を肯定してしまう人は少なからずいる。そういう人が同じ口で国による性的マイノリティ「支援」を非難する人を責めるとしたら、滑稽というものだ。
政治による「支援」というコトバの使い方にも問題がある。もっぱら自発的になされるものだけを支援と呼ぶべきなのであって、国が強制的に一方の国民の財産を他方へと移転することを「支援」と表現するのは、間違いのもとだ。
政府自体は、それこそまったく生産的ではない。ただ誰かの財産を誰かに強制的に移転しているに過ぎない存在だ。
もちろん、政治家や役人は、「支援している」と気取りたいだろうが、彼らは、ただ納税者から吸い取って、別の方向にばら撒いているに過ぎない。それを「支援」と呼ぶのはそもそもズルい。税金というものが、そもそも誰かが負担したものであるという観点をわざと隠しているのだ。
・子育て支援のために、非子育て納税者に負担させるべきである。
・LGBT支援のために、非LGBT納税者に負担させるべきである。
・〇〇支援のために、非〇〇に負担させるべきである。
と表現したうえで、強制負担させられる者の存在を許すべきなのかを丁寧に議論するべきだろう。
「誰かの生き方の価値を国家権力が評価して、別の人から強制的に財産を奪って配る」ということがまかり通っている。法の下の平等を履き違えているのは、与党だけではなく、野党の政治家も同じではないだろうか?
税金によって生き方にバイアスをかけようとすることは、一般にやってはいけないことなのではないだろうか?
http://shibari.wpblog.jp/archives/12876
http://shibari.wpblog.jp/archives/12638