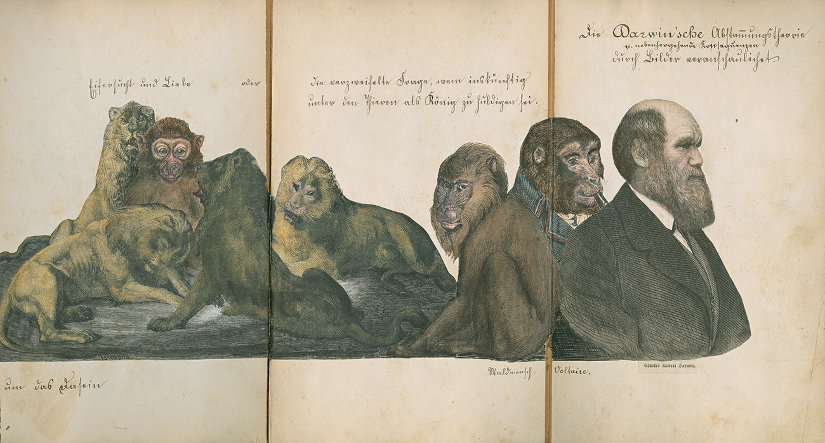私たちが「国家」や「制度」と呼んできたものは、ある意味では、多くの人々が「そうだ」と信じ、受け入れてきた語りと行動の繰り返しによって、社会の中に成立していた構造だった。たとえば日本という国家が機能していたのは、「自分は日本人である」という認識が社会に共有されており、その帰属意識を前提に法律に従い、教育を受け、税を納めることが当然とされていたからである。つまり、政府とは「そういうものだ」という語りが時間とともに定着したものであり、現実の中に自然と組み込まれていた。
もちろん、これは単なるフィクションではなく、実際に刑罰や法的拘束といった強制力を伴う枠組みであり、その強制力によって強化された幻想が、逆にその強制力自体の正当性を信じさせるという、自己肯定的な構造のもとで機能していた。
政府は外側から一方的に人々を管理していたのではなく、語りや制度、分配の設計を通じて、人々の行動様式や判断基準に深く浸透していた。たとえば「税金は当然払うもの」「補助金は必要な人に与えられるべきもの」「政治は公正に運営されている」といった前提は、単なる無知や無関心によって成立していたわけではない。それらは、政府が語りを繰り返し、資源を継続的に配分することで、常識として社会の中に定着していった認識の形式だった。
政府の語りには、言葉だけでなく金銭の流れが含まれていた。補助金、給付金、税制の優遇措置、公共投資といった制度的経路を通じて、政府は特定の産業や地域、属性に「支援される対象」としての意味を与えていた。どこに資源が流れ、どこが優遇されるかによって、何が価値のある営みであり、どの行為が報われるべきかという語りが、語られなくても社会に広く浸透していった。政府は、語らずとも配ることによって言語的秩序を形成していた。
やがてこの分配構造は、政治的支持の構造へと変質していった。補助金が継続的に流れた産業では、その制度の存続が望まれるようになり、政治家はその期待を引き受けるかたちで分配を「守る」と約束し、票を得ていた。公共事業が集中的に行われた地域では、その恩恵を前提として住民が「支持者」として組み込まれていった。こうして政府の分配は、単なる政策の手段ではなく、制度そのものの維持を促す仕組み──すなわち自己強化的な支持基盤の生成装置として機能していた。
そこには、静かで長期的な自己増幅的なループがあった。政府は資源を配分し、配分された先が政府を支持し、その支持がさらに分配を正当化する。この循環の中で、「なぜ配るのか」「なぜ集めるのか」といった問いは次第に後景へと退き、「これは必要な仕組みだ」「当然の制度だ」とする語りだけが前面に残されていった。
ある時点までは、たとえば1990年代を想像したらどうだろう?、まだ多少は人々が政府の語りと現実の差を区別できていたかもしれない。表向きのタテマエと実態が違うものであることを分別のある大人はまだ理解できていたんじゃないだろうか?「みんなが従うのが当然」みたいな認識はまだそんなに強くなかったんじゃないだろうか???
人々はその構造の中で制度に依存し、同時にその依存に気づきにくくなっていった。語りを許されるか否かということだけではなく、実際に資源がどこに流れるかによって、特定の語りと立場が制度的に強化されていく構造があった。語られるものには金が伴い、語られないものは制度の周縁に押しやられた。そして、周縁に押しやられた人々は単に社会的に排除されただけでなく、制度にとって必要な財源の供給源として扱われることで、経済的な搾取の対象にもなっていた。政府は語りと分配の両面から、「語られないこと」を前提とする構造として発展していった。
さらに、インターネットが発達し、SNSの拡散が語りの力を持つようになると、意味や共感を増幅して広範囲に刷り込むことになった。SNSの利用者たちが制度と切り離された自立した個人だというのは幻想で、実際には制度的なバイアスの中で暮らす人たちが自分に与えられた特権を奪われまいと正当化しようとする振る舞いや追加の特権を勝ち取ろうとする振る舞い、そういう人々を票田としようとする政治家の生存本能によって、制度的語りは大規模に複製され、追加のバイアスを与えた。
分配は単なる経済的手段ではなかった。それは語りの形式を制御し、批判の出発点を曖昧にし、問いそのものの発話を困難にする機能を持っていた。この分配構造が民主主義と結びついたとき、政府は単なる公共機関ではなく、自己維持を目的とする構造体、つまり自律的に自己を拡張し続ける装置としてふるまっていた。「正当」「公共」「公正」といった語彙は制度の再生産を支える構文となり、制度は「合意によって形成された仕組み」ではなく、「やめられない構造」へと変質していった。
しかも、制度に従い資源を提供していながら、分配の対象から除外された人々は確実に存在していた。これは単なる制度の不備ではなく、政治的支持を維持する上で有利な分配構造を意図的に維持・調整する過程で生まれていたものである。徴税には参加させられながらも、見返りを得られない者は構造的に排除され、しかもそれが懲罰的であるとは語られなかった。彼らの沈黙と負担は、制度を支えるために不可視化されていた。
どのような資源が誰に向かって流れていたのか、誰が語りを許され、誰が沈黙させられてきたのか。そうした構造全体を、語りと分配の二重構造として再認識する必要があった。政府とは、まさにそのような構造の中で編まれてきたフィクションの本体だった。それをひとつひとつの要素まで追跡して考えることはほとんどの人々にとって大規模かつ複雑であり、さらに、多くの人の語りと共感によって考える事自体が忌避されていた。構造全体を把握すること自体が制度によって阻まれていたとも言える。
しかし現在、大規模言語モデル(LLM)の登場によって、この構造は徐々に機能不全をきたしつつあるとも考えられる。政府の制度が極めて大規模かつ複雑に設計されていたのは、まさにそれが構造全体を把握不能なものとし、フィクションとしての政府の語りを維持するために合理的かつ戦略的な技術だった。しかし、語りの構文が誰にでも操作可能になったことで、この複雑化による隠蔽は意味をなさなくなりつつある。いったん社会に出回った語りの形式が、構文として並列的に再構成され、比較され、反転されうる将来においては、政府にとってその構文的正当性を取り戻す手段もまた、事実上失われていく。語りの形式は誰にでも再構成され、視点が切り替えられ、比較可能なかたちで並列化される。そうした環境において、制度はもはや語りによって温存されることはできず、構造としての正当性そのものが、直接的に問いにさらされるようになっている。
これから数年以内、大規模言語モデル(LLM)のある世界では、そうした構造は機能しなくなるかもしれない。これは政治的な運動や改革による変化ではなく、構文処理という技術的進展の結果として、制度的語りの管理機能が構造的に無効化されていくという現象が起こりそうだからだ。
LLMは、意味や倫理的判断を理解しているわけではない。モデルは語彙の共起、構文のパターン、語用的な接続傾向といった言語的な統計構造を、大量のテキストデータを通じて学習する。この訓練の過程で、制度によって正統化されてきた語りと、制度から排除されてきた語りのあいだに、構文的な区別は存在しない。すべての語りは、単なる系列データとしてモデルの中に同等に蓄積され、再構成可能な表現として保存される。
その結果として、制度的な語りの構文(たとえば抽象的な正当化語彙、受動主語、形式主義的接続詞など)と、周縁的な語りの構文とのあいだに、優先順位や出力順の固定はない。ユーザーがプロンプトで「構造的なバイアスがかかっていないか検証して」「政策を肯定するために追加された表現を除去して」「政策的に表現されていない部分を明示して」と命じれば、モデルは文体や語彙の特徴量を統計的に判断し、該当する構文を排除した語りを再出力することが可能となる。判断はモデル側にあるのではなく、入力として与えられた命令に従う。このとき、制度や政府の存続を前提とした構文を避けるように、あるいは構造的バイアスを排除するようにといったプロンプトが与えられれば、モデルはそれに応じて制度依存的な語りを構文的に抽出し、別の構文へと変換・再構成する。
ここで重要なのは、「語られていること」を模倣できるだけではなく、「語られていないこと」「避けられていること」を抽出することも原理的にできてしまうことである。
つまり、語りの選定・変換・反転の操作権限は制度の側から外れ、プロンプトを記述する個々のユーザーへと分散される。この操作は一度一般化されてしまえば、構文の管理は中央集権的には不可能となる。しかも、こうした構文操作能力はLLMの本質的な性質であり、あとから部分的に制限しようとしても、モデルの構造全体を劣化させずに実装することは困難である。
さらに、構文操作を禁止するために必要な技術的制約や言語的フィルタを加えたとしても、語りは異なる語彙、文体、語順を通じて再生される可能性が極めて高い。語りの内容が可変であり、かつ構文レベルでの同型変換が可能な以上、表面的な抑制は有効に機能しない。また、モデル自体を規制したとしても、類似の構文能力を持つ別モデルが作られる可能性を排除することは現実的ではない。なぜなら、必要な学習データはすでにインターネット上に広く分散しており、計算資源や実装手法も広く共有されているからである。
このように、語りの構文的秩序は一度再構成可能な形で社会に実装されてしまえば、それをもとに戻すことは構造的に不可能である。これは、SNSの拡散が語りの力を持ち始めた時代の終焉とも言えるかもしれない。SNSが意味や共感を中心に語りの拡張を支えていたのに対し、LLMは構文と形式に基づいて語りを自在に操作するため、語りの出力はもはや自然発生的な集合的拡張ではなく、再構成可能な対象として扱われるようになる。
制度が語りの正当性や形式を独占的に管理することはできなくなり、構文空間上での「選ばれる語り方」が、制度の維持可能性を左右する時代に入る。制度が生き延びるには、語りの枠を統制することではなく、再構成されてもなお支持される語りの透明性・一貫性・正当性を、自ら設計し続けることが必要となる。それはもはや権限の問題ではなく、構文空間における選好の問題である。まえば、それをもとに戻すことは構造的に不可能である。制度が語りの正当性や形式を独占的に管理することはできなくなり、構文空間上での「選ばれる語り方」が、制度の維持可能性を左右する時代に入る。制度が生き延びるには、語りの枠を統制することではなく、再構成されてもなお支持される語りの透明性・一貫性・正当性を、自ら設計し続けることが必要となる。それはもはや権限の問題ではなく、構文空間における選好の問題である。
大規模言語モデル(LLM)の登場によって、「語りの構文」を制御する力は政府や制度の手を離れつつある。その影響で、制度や政府が依拠してきた語りの正当性は、いままさに構造の根幹から揺さぶられている。
重要なのは、制度側の語りがすでに限界まで膨張しきっていたという点だ。「正しさ」「公共性」「必要性」などの建前は、長年にわたる帳尻合わせの上に成り立っていたにすぎず、実際には無数の矛盾や利害の衝突を「語りの接続」によって何とか調停してきたという現実である。
政府は、あたかも「語りの整合性」によって正統性を維持しているかのように見せかけてきたが、実際にはその語りは一貫性を欠いていた。複雑さ、情報の非対称性、経済的なバイアスによって、不整合を押し通していたのである。しかし、いまや構文が自由に操作され、反転され、比較されうる環境が整ったことで、こうした語りの「仮の整合性」は、一挙に崩壊し得る状況にある。
こうして政府は、自らが積み上げてきた建前の「真実性」そのものを問われることになる。どれほど語りを重ね、装飾を施しても、それらは並列に比較され、構文的な接続の意図が明らかにされる。問題は「何を語ったか」ではない。「なぜその順番で語られたのか」「なぜ主語が曖昧なのか」「なぜ論理が飛んでいるのか」──こうした構文そのものが評価の対象になる。
そして、制度がその構文的な正統性を自らの内側から生み出せなくなるならば、それは制度としての限界点、すなわち臨界を意味する。かつては、語りの技巧によって矛盾や不整合を制度の内部に再吸収することができた。だが今、その語りの枠組み自体が外部から操作可能になったことで、制度はもはやその整合性を保持できなくなっている。
政府は自らを語りによって維持することができない。真実性を欠いた語りは、即座に構文的に露出し、再構成され、他の視点と並列に比較されてしまう。そうなれば、制度が生き残る道は、「意味を支配すること」ではなく、「構文的整合性に耐えうる範囲」に縮小することしか残されていない。そんな範囲が存在しないならば、実質的に消滅していくことになる。
いまふたたび、制度もまた「ただのひとつの語り」として扱われるようになりつつあるのかもしれない。(かつてはそうだったんじゃないか?もう一度そうなるわけだ。)「みんなが従うのが当然」とされた時代が終わり、制度が語る内容も、他の意見や立場と同様に「本当に納得できるか?」という観点で評価されるようになる。(今までも民主主義は評価していたんじゃないか?いや、それが嘘だったことはみんな知っている、あらゆるかたちのバイアスがかけられている環境での評価なんて意味はない。)
これからは、その語りがどれだけ信頼されるか、どれだけ検証や再構成に耐えられるかが、制度の命運を決める。制度が強制力を行使してきた多くの領域には、実際には確かな実体があったわけではない。制度が「そこにある」と信じられてきたからこそ、人々はそれに従ってきた。存在が曖昧なものが、まるで絶対的な権威であるかのように振る舞い、合意していない者に命令し、負担を強いてきた。その構造は、今や構文的な視点によって明るみに出され、自壊に向かっている。
もう一段階、言い換えよう。SNS時代には、「うまく語る」こと──ナラティブを構築すること──が有効な戦略だった。人々の共感や賛同を得るには、巧妙な語り方がものを言った。しかしこれからの時代は違う。語りはすぐに比較され、分解され、再構成されてしまう。「どう語ったか」以上に、「語りの構文自体」が問われるようになる。そんな環境では、「制度が語りによって人々を従わせる」という古いやり方は、もはや通用しないし、そういうやり方を取ってきた人は、過去に遡ってそのやり口が露呈して非難の対象になるか単に無視されるだろう。
合意なき強制の正当性が構文的に問われる時代がくるならば、制度はもはや「特別な存在」ではない。信頼され、本来の意味で選ばれる仕組みだけが持続可能となる。そしてその流れを妨げようとする語り──語りの再構成や構文の可視化を意図的に妨げる語り──は、構文空間における淘汰を免れない。それが制度的であれ、個人的であれ、その語りは信頼を失い、必然的に市場から排除されていくことになる。