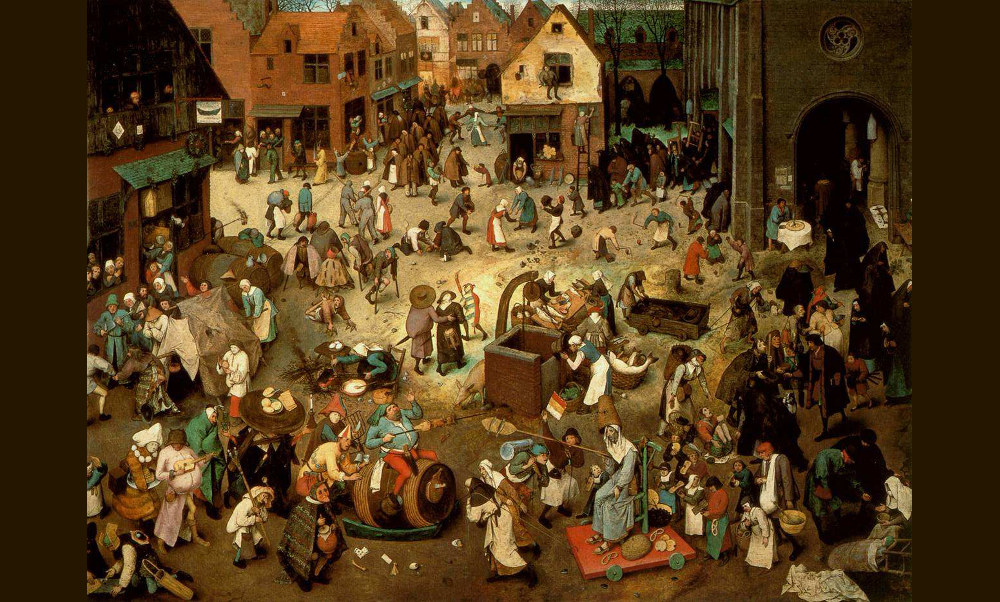政府による統制の存在しない自由な社会における犯罪者の扱われ方について考えたことをメモする。
月: 2018年9月
信仰と自由
あたりまえのことなのだけど、宇宙にもともとある法則を除けば実際に神が人間に強制したことなんてない。現実に強制しようとするとしたら、いつも人間である。
宗教というものは、経済法則や物理法則があるときに、何かを守れば得する傾向が強くなり、何かを無視し続すれば損する傾向が強くなるということを、ある時代の人が必死に考え、そのアイディアが市場にテストされ、淘汰されずに生き残った結果だ。
宗教の中に神が人間に干渉する様子が描かれるとしても、それを説明するためのフィクションにすぎない。
歴史の中で淘汰されずに残った宗教は、後の時代に権力によって加えられた解釈を除けば、少なくとも始まりの時点では自由意志をとても大切にしている。
そもそも道徳というものも、自発的になされる場合にだけ意味があるものであって、そうでないとしたら権威や権力が肥大してやがて行き詰まり、崩壊してしまう。そういうタイミングで現れる宗教改革者はいつも、権威や権力による強制を否定し、内心の自由に信仰を戻せ、と原点回帰を訴える。
現代人は、弱い者を助けるために徴税して分配することを良しとしてしまいがちだ。そのためなら、権力が人々の財産権を侵してもよいと考えてしまうのである。しかし、その先に見るのは、権力や権威の膨張と、やがて訪れる崩壊である。
いくつかの宗教の中に現れる喜捨というものは、文字通り自発的になされるものであって、強制されるものではない。自由意志に基づかなければ喜捨とは呼ばないのだから、もちろん喜捨は財産権の侵害にはならない。消極的自由をないがしろにすると個人のレベルでも損するし、集団になってもいきづまる、というのはどうしようもないことだ。
現代であれば、経済学の中にもっと正確な説明がある。けれども、人類は古くから気づいているし、繰り返し、思い知らされてきた。合意に基づく交換によって成立する市場を、強制によって歪めてしまえば、無理が蓄積してやがて崩壊する。
市場原理というのは人間の意思でどうこうなるものではない経済法則なのである。