国立大学が国立行政法人化して20年近い期間が経とうとしている。
大学の中にいる人はしばしば訴える、『基礎研究が大切である。』これは、至極もっともな話である。科学に限らず、あらゆる学問の歴史を振り返れば、基礎研究をおろそかにして長期的な発達があったとも思えない。
頭脳が集積する大学という教育研究機関で行うべき研究は、大学でなくてもできる近視眼的な仕事ではないはずだ。
研究者はいう、いわゆる「競争的資金」ではなく、裁量で使える予算配分がもっと欲しいと。
自由な分業の結果として生じる大学
かつて欧州や米国で大学が発達したのは、なぜだろうか?
市場から、評価される価値を作り出すことが期待されたからである。
マイナーであっても、将来性を感じたり、価値があると思う人がたしかにいて、一定の出資や寄付が集まり、そこに大学が地位を得た。社会の余裕の一部がそこに投じられ、成果を膨らませた。
大学というのは、自由な社会における分業の結果として生じたものなのである。
非商業的な大学(役人のための大学)
日本の大学には、国が「計画」に基づいて予算を配分し、企業が政府予算を獲得するための窓口として大学を利用するという役人中心の構図がある。
大学の中の人は、「競争的資金」の導入によって何ら「健全性」が高まっていないと嘆く。だが、それはまったく当たり前のことである。「競争的資金」という言葉が正しく表現するように、「市場における自由競争ではない」からだ。
あくまで、互いの合意に基づく取引こそが商業の基本である。互いの合意によって行われる取引が価格を形成するからこそ、自由競争には健全性を保つ機能がある。政府の強制力でもって集めた税金を配分する大学は、消費者に望まれる物が選ばれ、望まれない過剰供給が淘汰されていく自由競争の下に置かれていない。
政治の強制力によって集めた税金を基礎とする限り、役人が何といっても、それは商業の着ぐるみをかぶったお役所仕事に過ぎない 偽物である。政府の強制力で押し通すことは、商業ではなく、政治(暴力)だ。
いくら役人が「産学官共同研究」とか「コスト」とか「合理性」といった、それっぽいキーワードを並べているとしても、政府の強制力に基づく限り決して商業的態度とは言えない、政治的(暴力的)なのである。
「強制的に税金を奪って彼らを優遇しよう」みたいな話に健全性なんてあるはずがないし、税立大学の健全性なんて問うこと自体がナンセンスなことだ。存在自体が不健全なものを、あって当然のものとして健全性を議論なんてしたら、迷子になって当然だろう。
まったく残念なことに、研究者たちが一年のかなりの時間を、紙切れを埋めるためだけに費消してしまっている。国の予算を獲得する競争がし烈になっているからだ。研究者は政府の方針に整合するように申請書を調整し、予算申請の紙切れを書く役割を負わされる。大学は研究資源を納税者から搾取するための手段に過ぎなくなってしまった。
科学実験は巨大化したが、その要素は既知の成果の寄せ集めばかりになり、本質的な成果が生じにくくなっている。計画の途中で関心が変化しても、今や研究者は身動きすることができなくなっているからだ。
そこに適合しない研究者は居場所を失っていく。そこにあるものは、縁故資本主義的な窮屈な競争であって、市場における自由競争とは程遠い。
その窮屈さに耐えられない才能が、今この瞬間も虐殺されている。
税金か寄付か
大学の中の人は、「寄附文化が発達していない」などといって嘆く。そして、日本には寄付する文化が発達していないから税金を必要だと主張したりする。
だが、大学が税金によって維持されるものである限り、寄付が集まらないのはまったく当たり前のことだ。税金依存と寄付というのは、そもそも排他的なものなのである。
民間企業が寄付しようにも、寄付する動機があらかじめ奪われている。大学に関与する企業は、自力で基礎研究に手を出すよりも、公的研究機関に頼ることを選ぶようになった。公の予算でリスクなしに成果を得ようとする方が簡単だからだ。
だからといって、利用できるものを利用しなかったら、もちろん税金を搾取される側になってしまう。民間企業の経済的余裕が、あらかじめ税として奪われているのである。だから、寄付する余裕はそもそも失われている。
税金による大学は、もちろんその構造の一部なのである。大学に協力する企業は、実際のところ、強制的に奪われた税金をなんとか取り返そうとしているに過ぎない。
税金に依存すればするほど、大学に寄付する意味は失われる。
政府の強制力による大学に自由はない
将来性を感じたり、価値があると思う人が望んで出資するのではなく、誰かから税金を奪って役人の計画に基づく大学を作ってしまったらどうなるだろうか?
余裕のある人が資金を提供する場合なら自由な研究も許されやすい。けれども、余裕のない人から奪うことまでは許されるだろうか?
もちろんそんなことは、本来なら許されそうにない。だが、それを無理やり押し通そうとするのが税金による大学というものである。
国家が税という形で強制的に集めた有限なリソースを配分するとき、その研究と他の事業が比較されないなんてことはあり得ない。だから、大学の研究者には「社会を説得するためのコスト」が必然的に生じる。
だがもちろん、研究というのは他人に分かりやすいから素晴らしいわけではない、基礎科学の研究を万人に理解できるように説明できるとしら、それは教科書が執筆できるほど研究が成熟してからである(それでもなお、万人に理解させることは難しいだろう)。
大学の予算配分をデモクラシーに頼ってしまったら、予算は政治や役人の無責任と抱き合わせでやってくる。決して自分の金ではないという負担の強制に由来する無責任が、「分かりやすさ」「成果のだしやすさ」を求める。だが、そこには意味が伴わない、単に納税者から金を奪うタテマエに過ぎないのだから、当然だろう。
大学という機関の内側で無駄遣いする傾向が膨らんでいくとすれば、それは効率を優先する商業的動機の結果ではなく、効率を無視する権力によって他人の金を使って成果を持ち去りたいという政治的動機に基づいているからだろう。
本質的に不可能なことを政府の強制力で押し通しているだけだから、余裕があろうとなかろうと関係なくコストやリスクが無視され、無責任になってしまう。
公の資金を使って自由な研究をしようとすることは、原理的に無理なことを押し通しているだけだから、そもそも無理なのである。
自由な社会における大学(それが本来の大学)
研究者は自由に「大胆さ」を求めるかもしれない、だがそれが政治的動機に支えられている限り、大胆というより乱暴なものである。
公権力から学問が経済的独立を取り戻すことによってようやく、自由な学問の発達を見ることができる。研究資金は、そもそも民間から直接資金が入ればよく、文科省や独立行政法人を経由する必要がない。そこに価値を見出す人が出資したり寄付したりしてもらえばよく、望まない人に負担を強制してもよい道理なんて、そもそもなかったのである。
「国の科学研究予算」を無くすことは、国の中から科学研究が消えることを意味しない。単に、役所を介して(役人の介入を前提に)予算を分配しないからといって、科学研究を行う動機が個人や企業から消えるわけではないだろう。(それとも研究というものは、その程度の動機で行われていたのか?)
大学への政府予算を無くし、民間に任せた場合、企業は簡単に売れる仕事や役人にウケる流行り仕事ではなく、数年で成果を出せるような分かりやすいテーマばかりではなく、大学だからこそ生じる成果を求めて大学に投資するだろう。また、短期的というよりは長期的な関係を作って、学問を尊重し、協業しようとする態度を伴うだろう。大学という機関を利用するなら、その方が合理的だからだ。(大学というのは、あくまで自由な社会における分業の結果として生じたものだということを思い出そう。)
科研費やその他の国による研究予算の配分を廃止・縮小し、単に税を無くして民間に返すのでなければ、問題は膨らみ、軋轢が増えていくとしても、まったく仕方ないだろう。役所や独法が分配する競争「的」資金などではなく、大学は本物の自由市場から資本を獲得しないのであれば、学問の自由は生じるはずはない。
本来なら、大学の中の人は、マイナーな興味であっても、無駄じゃない、社会に必要されているのだ、と自信を持って言えたはずだ。
出資者と合意する、というまっとうな手続きさえ怠っていなければ。
http://shibari.wpblog.jp/archives/14917
http://shibari.wpblog.jp/archives/13193
http://shibari.wpblog.jp/archives/14056
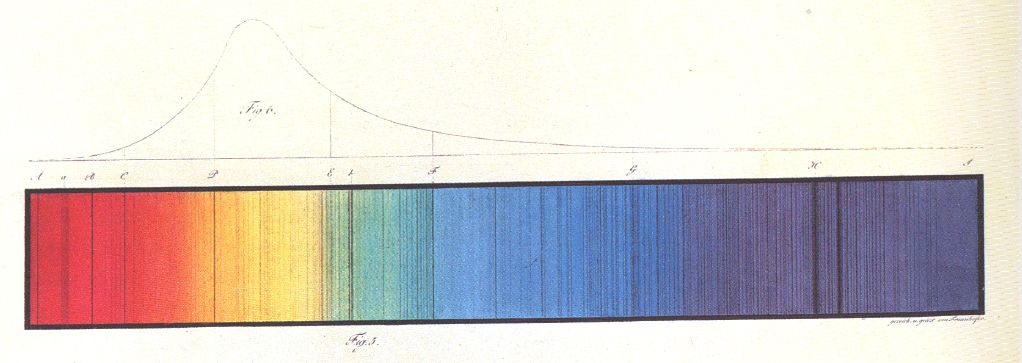
「国の科学研究予算って本当に必要ですか?」への2件のフィードバック