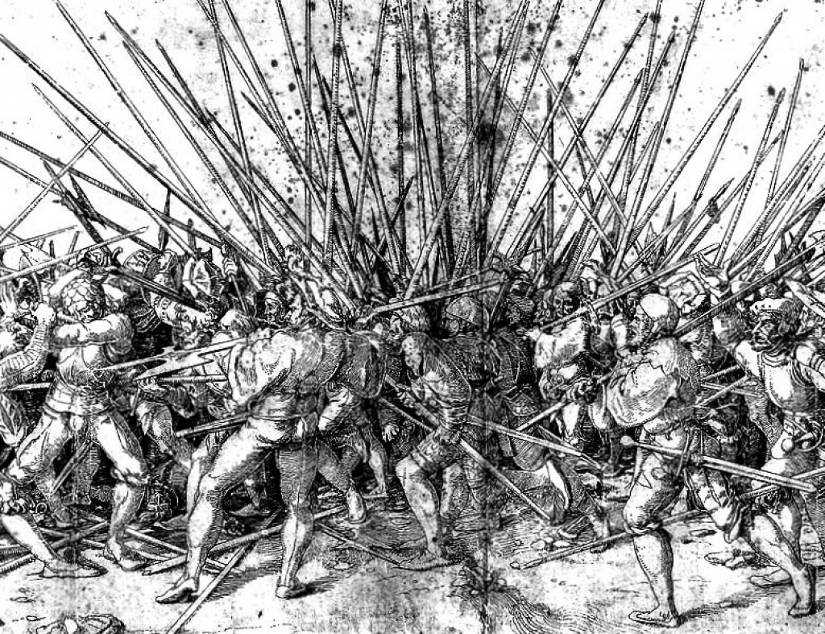抵抗権とは、そこに住む人々が不当に自由を奪う政府の権力行使に抵抗して体制を転覆する権利のことである。あるいは、革命権とも呼ばれる。自由を不当に奪う国家に対して抵抗する権利を失えば、自ずと国家は乱暴に振舞うようになっていくから、抵抗権は極めて大切な権利である。
日本国内で内乱が起きた場合に武力介入する前提でアメリカ合衆国の軍隊が駐留するということがそもそも日米安保体制の前提だった。
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(いわゆる旧安保)は、その第一条で内乱への言及があった。これは、内乱条項として知られる。
第一条(アメリカ軍駐留権)
日本は国内へのアメリカ軍駐留の権利を与える。駐留アメリカ軍は、極東アジアの安全に寄与するほか、直接の武力侵攻や外国からの教唆などによる日本国内の内乱などに対しても援助を与えることができる。
在日米軍が強い地位を維持し、日本政府の責任の範囲外で行動できたことから、日米安保条約は実質的に日本に住む人々の抵抗権を奪うものだったと言ってよいだろう。外国軍の駐留と、その実質的治外法権を認める日米安保条約は、日本人から抵抗権を奪い、権力を肥大させた深刻な原因のひとつとなった。
国家が人々が自ら身を守る自由を奪い、武装を独占する。のみならず、議会や自国の法律によってそれを制限することまで放り捨てたのが内乱条項だったのである。
表面的に廃止されたとはいえ、地位協定の形にわかりにくく変形しただけで、実質的には日本国内の内乱に際して軍事介入できる状態を維持するという当初の機能を維持している。内乱条項そのものは1960年の安保更新において名目的に廃止されたが、同時に設定された日米地位協定が在日米軍に高い地位を与えた。日本国内にありながら在日米軍に日本の法令は適用されず駐在公館(将兵個人には外交官)並みの治外法権・特権が保証された。
1952年の日米安保条約成立以降、効果的に抵抗権が抑止されたことによって、日本政府は人々の抵抗を恐れずに乱暴な政体構築を進めることができるようになった。日本政府は米国政府による保護を前提に乱暴な政体構築を進めたのだから、日本政府が米国政府への従属を強めたとしても当然だった。後ろ盾を失えば、多くの無理を放棄する必要に迫られるか、さもなくば政権を転覆される。そういうバランスの上に体制が構築されていったのである。
日米安保条約が非難されるべきなのは、条約が日本に住む人々の抵抗権を実質的に奪ってきたからである。体制構築の初期段階で、実質的に抵抗権を奪う建前が導入され、そこに押し寄せる批判をごまかす過程でさらに多くの建前が導入された。
結局、日米安保体制を押し通すために多くの政治的利権が作られ、人々の経済的自由は次々と政府に奪われていった。
日米安保推進の最も強い口実は、ソビエトへの対抗、反共というものだった。けれども、実際には日米安保体制は日本政府を権力に都合よく肥大させ、人々から自由を奪う大きな原因になった。反共を口実として自由主義の保護を掲げながら、反共というよりむしろ共産化の道を作り出したのである。
http://shibari.wpblog.jp/archives/14078
http://shibari.wpblog.jp/archives/13244